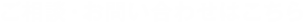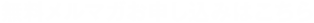民法改正の人事への影響
人事の役割は労使間の債権をうまく機能させることである。
人事に関係する法律といえば、労働法です。正確にいえば労働法という法律はなく、労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法など、働くことに関係する法律を総称したものが労働法となっています。このコーナーでも、労働法の改正動向を折に触れてお伝えしておりますが、今回のテーマは民法改正です。実は、民法と人事は多いに関係があるのです。というのも、労働法(労働基準法と労働契約法)は民法の特別法であって、現在でも労働法に記載のない事項は民法の規定で判断されているからです。その民法が約120年ぶりに大きく改正されようとしており、その内容を理解しておく必要があるでしょう。執筆はHRmics副編集長の荻野です。※2014/01/16の記事です。
セクハラによる損害賠償が認められる理由
民法は個人の権利義務関係を規定した社会生活の基本法である。現在の民法は1896(明治29)年に制定されたもので、1条から1044条まであり、極めて膨大だ。
民法は大きく2つに分けられる。財産法と家族法である。そのうち財産法は人と物の関係を扱う物権法と、人と人の関係を規定する債権法からなる。一方の家族法は家族内における権利関係を扱う親族法と、人が死亡した場合に必要な財産相続のルールを定めた相続法から構成される。
このうち、大きな改正が行われようとしているのが債権法の部分である。
債権とは何か。人が人に対して特定の行為を行うよう、請求できる権利、これを債権と呼ぶ。債権の多くは契約によって発生する。売買契約、賃貸借契約などだが、大事なものも忘れてはならない。そう、雇用(労働)契約も債権の一種なのだ。
もっとも、契約によらずして発生する債権もある。不当利得(を誰かが得た場合)であり、不法行為(を本人が受けた場合)である。詐欺の被害にあった人が犯人に返金を請求できるのは、それは犯人が不当に得た利益だからだし、加害者の故意や過失によって損害を被った人が損害からの回復を求めることができるのは不法行為による損害賠償請求を民法が認めているからなのである。
会社でセクハラ行為があったとする。セクハラは不法行為である。その場合、被害者となった社員は本人および会社に損害賠償を請求できる。不法行為による損害賠償を認める民法709条と、そうした人を雇用している使用者の損害賠償責任を定めた民法715条があるからなのだ。民法と人事業務はこのように密接に関係しているのである。
雇用契約は継続を旨とする点が他と違う
さて、本題に戻って、債権である。もう一度確認すると、特定行為の実行を促すことのできる権利が債権だが、その反対が債務である。特定行為の請求に対し、それを遂行する義務を負うことだ。
雇用契約の場合を考えてみると、会社は労働者に、債権としての労務給付請求権を有している。それに対して労働者は債務として労務提供義務を負う。また労働者は会社に対して賃金請求権という債権を、会社は労働者に対して賃金支払義務という債務を負っていることになる。
ただここで、雇用契約には他の契約とは異なる特徴があることを忘れてはいけない。
売買契約がまさにそうだが、多くは一回限りのことが多い他の契約とは違い、雇用契約は一定の継続を旨としている点が違う。
その関係が継続するためには、会社が事業体として存続し続けなければならない。使用者は労働者を組織化し、効率的に働いてもらう必要があり、そのために使用者には配置、異動、降昇格、解雇なども含めた指揮命令権が広範に認められている。
また、会社の事業が円滑に行われ、事業体が存続していくために両者は対立することなく、信義誠実の関係を保持することが重要となる。そのために使用者は労働者の生命を守り、健康で働けるよう配慮する義務を負い、他方、労働者は仕事上知った営業秘密の保持義務や退職時の競業避止義務を負っている。
このように、民法の枠組みで雇用関係を整理してみると、人事業務も新鮮に思えてこないだろうか。人事の果たすべき役割とは労働者と使用者の間に結ばれた債権関係を円滑に機能させることに他ならない。
債権法改正の理由とスケジュール
さて、改正問題である。なぜ今、改正されなければならないのか。
法務大臣の諮問機関であり、改正原案の作成組織でもある法制審議会によると、理由は二つある。
一つは社会ならびに経済変化への対応である。民法が制定された1896年は日清戦争終結の翌年である。車といえば人力車、通信手段としての電話がようやく姿を現した時代であった。それから幾星霜が経ち、世はグローバル社会に、そしてネット社会にもなった。現行民法はその変化に対応できていない、というわけである。
もう一つの理由は国民一般にわかりやすいものに民法を作り変えるということ。具体的には、条文の外に形成された判例ルールの条文化、内容が不明確な条文の明確化、条文化されてはいないが、もはやスタンダードになっている原則や概念の条文化、という3つだ。
法曹界の一部では「民法改正など必要ない」という意見もあるようだが(鈴木仁志著『民法改正の真実』参照)、改正作業はすでに相当、進んでいる。2009年11月から2011年4月に法制審議会で論点整理が行われ、2013年2月には中間試案が発表された。それに対するパブリックコメント(意見公募)手続きが同年4月から6月にかけて行われた。早ければ今年中に改正要綱案が作られ、2015年の通常国会に提出される運びだ。
ボーナス規定の見直しが必要か
民法のなかで債権法に相当する部分は399条から724条までであり、これまた膨大な内容だ。人事や雇用に直接関わる点に絞って、どのような改正が考えられているか、想定される影響も含めて、中間試案(以下、試案)を見ておこう。
まずは、わかりやすい、雇用に関する直接規定から。
報酬(労務の履行が中途で終了した場合の報酬請求権)についての改正が提案されている。労働者が労務を途中まで遂行したのにもかかわらず、何らかの事情で果たせなくなった場合、既に行った仕事の割合に応じて報酬を請求できるようにする案である。また、その原因が使用者にある場合、労働者はそれに対する報酬額相当の反対給付を請求できるという規定を入れることも検討されている。
ごもっとも、とうなずいてしまいそうだが、ちょっと待ってほしい。これが認められると、ボーナスの支給規定を見直さなければならなくなる可能性がある。なぜか。通常年2回支払われるボーナスは半年間以上、在籍した社員のみに支給され、中途入社で入ってきた社員には支給されないという規定を置いている企業が多いはずだ。仕事の割合に応じて報酬を請求できることになった場合、ボーナスも労働の対価ととらえるならば、半年間在籍した社員には支給されるが、5箇月間、在籍した社員には支給されないという規定は民法違反になる可能性がある。同様に、ボーナス前に退社した場合も、当然、支給対象となる。
有期雇用については次の案が示されている。
現行626条(期間の定めのある雇用の解除)にこうある。
- 1、雇用の期間が5年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、10年とする。
- 2、前項の規定により契約の解除をしようとするときは、3箇月前にその予告をしなければならない。
雇用が終身の間継続?商工業の見習い?3箇月前に予告が必要?……明らかに時代錯誤の規定である。
そこで試案は以下のように改めることを提案している。
期間の定めのある雇用において、5年を超える期間を定めたときは、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約を解除することができるものとする。それによって契約を解除しようとするときは、2週間前にその予告を行わなければならない。
期間の定めのない雇用についてはどうか。現行627条2項に、解約の申し入れは次期以後、同3項に、6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合の解約の申し入れは3箇月前、という規定がある。これについては労働基準法20条に、30日前の解雇予告または手当の支払いを義務付けた規定がある影響で、事実上死文化していることから、2項および3項の廃止が検討されている。
いずれも納得の行く改正内容である。
ちなみに、民法から派生した労働法が、大本の民法と異なる内容を示している場合は、労働法の方が優先される。これは、労働法以外の特別法と民法の場合でも同様となる。
賃金の時効が2年から伸びる可能性
時効についても改正が提案されている。労働関係でいえば職業別に細かく定められた短期時効が廃止されるのだ。現行民法においては賃金の時効は1年となっている。中間試案では賃金を含む短期時効を5年とする甲案、3年、4年、5年のいずれかを併存させる乙案が記されている。
一方で退職金を除く賃金については、労働基準法115条で時効が2年とされている。民法の特別法であり、労働者保護をうたう労働基準法において、「民法よりも短期の時効を定めるのはおかしい」という声が労働界などからあがっており、もしこの通りに民法が改正されると、早晩、労働基準法も改正され、賃金に関する時効が長くなる可能性がある。そうなると、たとえば企業が労働者から残業代支払訴訟を起こされた場合、負担が大きくなるのは必至だ。
その場合、過去の賃金については法定利率が適用されることになる。試案はこの法定利率の引き下げを提案している。企業にとっては朗報である。現行の利率は5%。この低金利時代、明らかに過大だ。試案は3%を基本とし、年1回の基準日に0.5%刻みで変える変動利率制への移行を提案している。
就業規則の公開が義務付けられる日
今回の民法改正の目的の一つが社会変化への対応だと先に書いた。試案に記載されているその端的な例が約款に関する記載の提案だ。生命保険に加入したり、インターネットで商品を購入したりする場合、細かな文字が書かれた書面をもらったり、パソコン画面上に詳細な利用規約が表示される。それが約款である。
あらゆる契約は当事者がお互いに内容を確認し、合意をすることで成り立つものだが、不特定多数を対象とした契約の場合、個別に契約を締結していたら、時間や手間がかかり、すこぶる非効率である。そのために登場したのが約款だ。記載内容について明確な合意がなくても、それに従う意思があったものとなる。この約款に対する取り決めが現行の民法にはまったくないので、何らかの記載が検討されている。
労働契約における約款とは何か。就業規則が極めてそれに近い。
試案では、契約の当事者がその契約に約款を用いることに合意し、なおかつ、その約款を準備した者が、契約締結時までに相手が合理的な行動を取れば約款の内容を知ることができる場合、約款が契約そのものになる、という規定を置くことを提案している。
つまり、約款を契約に用いることに対する双方の合意、その約款内容が開示され容易に見られる環境、この2つが不可欠になると言っているのだ。
一方、就業規則については労働契約法7条に次の定めがある。
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする
ここでは内容の合理性と周知があれば足り、労使双方の合意も、事前チェックの環境整備の必要性もうたわれていない。とすると、就業規則は民法の定める約款ではなくなってしまう。それならそれでいいのかもしれないが、就業規則を約款足りえるようにする規制が労働契約法に付け加えられる可能性がある。会社のホームページに就業規則の開示が義務づけられ、その企業への就職を考えている人ならいつでもチェックできる環境を整えること、入社の際には就業規則の説明とそれを労働契約とすることに関して労働者の合意を得ることが必要になるかもしれない。人事にとって手間とリスクが加わる可能性がある。
労働条件が劣悪で、若者を使い捨てにするような企業への風当たりが強まっている。昨年末には厚生労働省が立ち入り調査に乗り出していることはご承知の通りだ。労働という表現を使うと、どうしても仕事をあげる側、もらう側の上下関係が想起されがちだが、雇用は契約の一種であり、会社と労働者はそもそも対等の関係にある。そのことを認識すれば法令違反も減るはずなのだが…。そのために労働法だけではなく、民法の知識が役立つのではないだろうか。せっかくの機会である。120年ぶりの改正をきっかけに、民法の知識を深めることをお勧めしたい。
●採用成功ナビの2つの特長
最適な採用手法をご提案!
様々な企業が自社に合う
人材の採用に成功している
豊富な採用実績!
多岐にわたる採用事例から
自社に似たケースが探せる
お申し込み・お問い合わせ・ご相談はこちらからお気軽にどうぞ!
採用サービスのご利用について
すぐに採用を始めたい方も。まずは相談してみたい方も。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

メールマガジン(無料)について
中途採用情報メルマガ(無料)を定期的にお届けします。
- ・求職者の詳細な職務経歴情報が閲覧・検索できる
- ・中途採用に役立つ最新情報や採用の秘訣などをお届け
貴社の事業成長に少しでもお役に立てられれば幸いです。