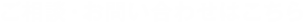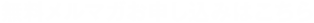新有期雇用法制を考える(後編)
「多様な正社員」を生み出す孵卵器となるか
労働契約法の一部を改正し、有期労働の契約期間に制限を加える法案が今国会で成立しました。前回に引き続き、この問題を取り上げます。今回は、その中心条項である「活用上限期間の設定による、有期から無期への転換」にスポットをあてます。執筆はHRmics副編集長の荻野です。 ※2012/08/23の記事です。
有期から無期への強制転換
今回、最も大きな改正となるのが、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、期間の定めのない契約に強制転換させる仕組みの導入である。
アルバイトとして雇った学生が大学を1年留年して働き続け、はや5年、自動的に正社員になってしまう、ということなのか。いや、違う。そこにいたるまでに、いくつかの歯止めが用意されている。
ひとつは、労働者の申し込み。つまり、正社員になりたい、と自ら申し出なければそうはならない。もうひとつは、労働条件は従前のままでいいこと。つまり、店舗従業員だったら店舗での仕事と待遇が続くわけで、その日を境に、事務スタッフの正社員になるわけではない。三番目として、派遣法と同じく、クーリング期間が設けられている。労働契約期間が1年以上の場合は6ヶ月、それ未満の場合はその期間の半分、その仕事に就いていなければ、期間に換算されない。
さらにいえば、5年という期間換算の開始は改正法の施行後となる。それまでに何年間、働いていようが、その期間が合算されることはない。
こうした歯止めを、労働者側は「手ぬるい」と批判する。たとえば、日本弁護士連合会が、この4月に、「有期労働契約に関する労働契約法改正案に対する意見書」を発表しているが、その中で、①上限5年は長過ぎるから1年、せいぜい3年にすべき、②クーリング期間は撤廃せよ、③無期転換後の労働条件は有期の時と同一でよい、という条項は削除すべき、と述べているのが代表例。前回書いたように、これは有期労働法制が世界一厳しいフランス並みの規制であり、副作用が大いに心配される“劇薬”に思える。
2年が有期の上限となった韓国では
一方で、この仕組み自体が引き起こす、より深刻な副作用を心配する声も上がっている。それは何かというと、有期から無期への転換を恐れる企業が、5年が終わる直前での雇止めを促進させ、ただでさえ不安定な有期雇用者の身分をさらに不安定にさせるのではないか、という危惧だ。
この問題に関しては、お隣、韓国の例が参考になる。2007年7月1日から、「期間制および短時間労働者保護等に関する法律」(非正規労働者保護法の一つ)が施行されているが、その中に、出口規制として、企業が有期雇用者を2年を超えて活用する場合、期間の定めのない労働契約を締結したものとみなす、という条項が組み入れられているのだ。その結果、どうなったか。果たして、2年未満の雇い止めが増えたのか。
この問題に詳しい弁護士の小林譲二氏によると、大きな影響は出ていない、という。
具体的には、法律施行前における有期労働契約の雇止め率は44.6%(韓国経営者総協会調べ)。施行後の2010年6月から2011年7月までの14ヶ月において、1年6ヶ月以上、2年未満の有期労働契約のうち、契約終了、つまり、雇止めとなったものは、46.15%だった。施行前が44.6%、施行後が46.15%、大きな差はない(それ以外は、正規職への転換が約22.33%、そのままの継続雇用状態が31.5%)。
有期雇用が可能な年数の上限設定と、それを超えた場合の無期転換という政策の導入により、期間満了前の雇止めの増発、という事態は、少なくとも韓国においては起こっていないのである(以上、『季刊労働法』237号掲載の同氏の論文「韓国の非正規労働者保護法の実情と日本」による)。
研究者には例外措置を、という声も
さて、この問題に対して、思わぬところから横槍が入った。内閣府に設置された政府の総合科学技術会議である。大学や各種研究機関では多くの研究者が有期労働契約で働いているが、国立大学などでは特に人件費の削減が義務付けられており、期間の定めのない雇用を増やす余裕はない。その結果、上限となる期間5年前の雇止めが増えるのではないか。そうなったら、若手研究者の雇用環境が悪化し、研究者を志す若者が減るかもしれない。それは日本の大学や研究所、ひいては科学・技術研究の存続の危機につながるのではないか、というのだ。
「労働契約法改正案に関する論点メモ」において、データとして上げられているのは、地方国立大学の例。全教員(助手・助教・講師・准教授・教授)2,965名のうち、任期付きの有期雇用扱いの人が52%、そのうち、勤務5年を超えている人が63%で、全教員の33%にあたる。厚生労働省の「有期労働契約に関する実態調査」(2009)によると、全産業のうち、有期雇用比率が高いのは「宿泊業・飲食サービス業」で35.9%、次が「教育・学習支援業」で32.8%だから、「全教員の52%が有期」という数字はそれよりも高いレベルだ。
しかも、補助的労働力が有期雇用の諸産業と違い、明日を担う若手人材ほど有期の割合が多いのだ。確かに、憂慮されるような「副作用」が過大となれば、深刻な問題になるだろう。
ただ、この背景には、卒業後の就職の問題をきちんと考えず、大学院に進学する学生が多いという問題がある。いわゆるポスドク過剰問題である。この、5年で区切りがつく仕組みが、その博士熱を冷まさせるきっかけになるのではないか。プロ野球選手だって、Jリーガーだって、期限つきの年俸制の世界だ。どこだってプロの世界は厳しい。有能だが、万年助手で、任期つき雇用を何度も更新してきた人はこの仕組みで救われるだろう。一方で、プロの研究者として通用しない人材は、「任期なし」になれない自らの適性を自覚したうえで、別の道を探す。これは本人の問題だけではない。大学や研究機関も、若手のうちは誰でも有期雇用で、という乱暴なやり方ではなく、それこそ、ふさわしい人材をきちんと選抜し、それぞれに応じたキャリア設計を考えるべきだ。そういう大学や研究機関にこそ、優秀な若手が集まるようになるだろう。そういう形で、この仕組みが機能していく可能性もあるのではないか。
「途中から正社員」の人事管理を
最後に、企業の人事管理への影響を指摘しておきたい。勤務5年を経て、本人が正社員を希望した場合、企業はその人を期間の定めのない正社員にしなければならない。その中から、よほどできる人材は「正規の」正社員としての抜擢があるかもしれないが、多くは有期の際の労働条件のままだろう。そうすると、「最初から正社員」という人材と、「途中から正社員」という人材の2つができる。そう、多様な正社員への道が開けるのである(ただし、来春の法施行の後、5年経ってからの話だが)。
従来の日本型雇用のもとでは、正社員とは、主に「異動、転勤、何でもござれ」の男性大卒のエリートを意味した。最近は、勤務地や職種を限定した多様な正社員モデルを設ける企業が増えているが、この有期からの転換社員がまさに新しいそれになる。濱口桂一郎氏がいうジョブ型正社員のモデルになるのだ。
先月、厚生労働省の雇用政策研究会が、日本の労働力人口が、2010年から2030年までの20年間に、約950万人減る試算を発表した。労働力が大きく減る時代は、雇用機会の創出とともに、一人ひとりの働き手の意欲の向上と能力開発が重要になる。私も契約社員として働いた経験があるが、どこか日々に“借り物”感がつきまとっていた。この法改正が、多くの労働者が高い意欲をもち、安心して働ける仕組みとして機能することを願ってやまない。
●採用成功ナビの2つの特長
最適な採用手法をご提案!
様々な企業が自社に合う
人材の採用に成功している
豊富な採用実績!
多岐にわたる採用事例から
自社に似たケースが探せる
お申し込み・お問い合わせ・ご相談はこちらからお気軽にどうぞ!
採用サービスのご利用について
すぐに採用を始めたい方も。まずは相談してみたい方も。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

メールマガジン(無料)について
中途採用情報メルマガ(無料)を定期的にお届けします。
- ・求職者の詳細な職務経歴情報が閲覧・検索できる
- ・中途採用に役立つ最新情報や採用の秘訣などをお届け
貴社の事業成長に少しでもお役に立てられれば幸いです。